僕は柔道整復師の資格を取得し、今は接骨院で働いている。
久しぶりに会う知り合いや初めましての方に、職業を聞かれた際、「接骨院の先生をやってる」と言うと、「あー!整体師か」とほぼ全員に言われる。
立て続けに、「肩が痛いから治してくれ」「体が硬いから一瞬で柔らかくして」と言われる。
僕は、医者でもなければ、マジシャンでもないから厳しい。
初めの頃はそう言われるのが嫌で、「整体師じゃなくて柔道整復師ね」と食い気味に突っ込んでいた。
なぜ整体師と言われるのが嫌なのかというと、
整体師 = 無資格
柔道整復師 = 国家資格
だから。
当人たちは、それを知らずに言っているのにも関わらず、自分のしてきた勉強を否定されているみたいで嫌だった。
今はそれを言われても基本的にスルーしているが、この業界に入って「柔道整復師 = 整体師」と言われるのも仕方がないと思った。
*
最近、医療界で何かと話題になる「直美(ちょくび)」。
直美とは、2年の臨床研修を終えた若手医師が、専門医の資格を取得せずに、直接「美容医療」の業界へ進むことを言う。
一体何故か。背景には、日本の勤務医の労働環境の厳しさが挙げられる。大学病院や高度医療を提供する病院などの残業時間が多いこと、人件費の増加や保険診療の点数が取れないといったことが医療機関の経営を圧迫している。このような状況で、自由診療である美容医療に可能性を持ち、業界へ進む医師が増えているのも不自然ではない。
でも現実は甘くはない。「自由診療で楽に稼げる」「労働時間が長いのが嫌だ」といった理由で美容医療の道に進んでも、ハイリスクが伴う。
同じような思考で美容業界へ進む医師、看護師などの医療従事者が溢れてしまえば、業界の競争は激しくなる。それに伴い、新たな技術やマーケティング、他のクリニックとの違いを示していかなければ、遅れたクリニックから埋もれてしまう。そんなのは、埋没だけで十分。
*
これは僕が在籍するこの業界にも重なるところがある。
現在、日本に存在する数多くの接骨院・整骨院で、保険診療のみでやっているところは少ない。と言うのも、本来の柔道整復師は「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷」の所謂「ケガ」において整復・固定や応急処置、後療法などが行える人のことを言う。しかし、日常生活やスポーツでケガをした際に向かうのはどこか。多くの人は「病院(整形外科)」に行くだろう。病院へ行けば、レントゲンが撮れる、信頼できる医師がいる、リハビリで改善を図る。
接骨院へ行く人はほぼいない。
とすれば接骨院・整骨院へ来る人はどんな人だろうか。「病院へ行ったが相手にされなかった」「慢性的な腰痛・肩こり」「神秘的なものを信じている人」などなど。
「マッサージ」と勘違いしている人も多い。マッサージは「あん摩マッサージ指圧師」の国家資格を取得した人が行える行為であって、柔道整復師や整体師は本来、マッサージと言ってはいけない。でも、マッサージと謳ってやってる院がごろごろあるけどね・・・。
ほとんどの人はケガをしたら病院に行く。接骨院・整骨院を訪れる人は、慢性的な痛みを抱える人たちが多い。接骨院・整骨院は保険を使用して施術が許されているが、それはあくまで急性のケガのみ。「さっき足を捻りました」「この前の大会で肉離れしました」だと保険が効く。「一ヶ月前の捻挫がまだ痛い」「去年に肉離れをしてから時々痛む」などは保険は効かない。それでも保険を使用していたりする院はたくさんあるのが現状。だから柔道整復師は、グレーと言われ、医療業界からどこか蔑まれた目で見られたりする。
*
接骨院・整骨院は保険の患者さんが少ない、慰安目的で訪れる人が多い。となれば、言わずもがな自由診療にシフトせざるを得ない。そして、回数券やキャンペーンなどのマーケティング方法で稼ぐ院がほとんど。まるでマジシャンかのように、その場で痛みをとったり、可動域を広げたりして、患者さんを驚愕させる。今でこそ、それで生きている院が多くあるが、数年後には潰れていると思う。
*
柔道整復師や鍼灸師は開業権を持ち、保険診療の接骨院や鍼灸院を開業することができる。
最近では資格を持たない人たちが整体師と名乗り、整体院を開業して自費の施術を提供している院も増えている。また、理学療法士や作業療法士など病院のリハビリルームで活躍している人たちにも独立したい欲が湧くことがよくある。彼らは保険診療の治療院を開業できないため、整体師として開業することが殆ど。
資格の有無に関わらず、人の身体を扱う職業である僕たち。
無知は恐い。
何もわからないまま、その院のマニュアルを叩き込まれ、ひたすら患者さんに触れお金を稼ぐ。
*
僕は柔道整復師になりたかったのであって、マジシャンではない。
これから自分のやりたいことのために、さらに勉強して、本当に僕たちを必要としている人たちのために仕事をする。


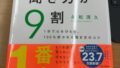
コメント